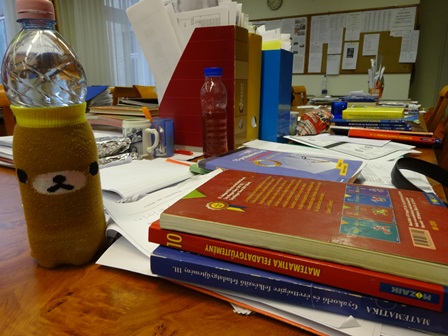フニャ高(←ワタシの勤め先の高校の仮の校名)はハンガリーの公立の高校です。
日本の公立高校の先生たちって転勤がありましたよね?
毎年4月には先生たちの移動があって、朝礼で新任の先生の紹介があったりした。
一方、フニャ高の先生には転勤がありません。(フニャ高の先生に転勤がないってことは、ハンガリーの公立学校はどこでも同様に転勤がないと考えて良いと思う。近年ハンガリーでは学校のシステムの大変革を断行しているので、この先どうなるかは分からないけど。) だから、フニャ高には『勤続20年以上!!』…みたいな先生が何人もいたりする。
フニャ高勤務10年以上の先生は かなり多いんじゃないかな? そういうワタシ自身が 何だかんだでいつの間にかフニャ高勤務6年を過ぎて、今が7年目だからね~(^^ゞ ワタシが来た時に 既にいた人は、少なくとも7年以上勤務している人たちなわけだ。
学校は9月から翌年6月までの1学年ごとのサイクルで動いているので、教員の勤務契約も1学年ごとが基本。 だから9月から新たに採用された先生は、翌年の6月の学年終了まではフニャ高に勤めることになる。 学年途中で先生が入れ替わるのは、何かと授業にも支障がありますもんね~。
でも実際には、学年の途中でフニャ高を去っていく先生が 毎年何人かは出てくるもんです。
今学年度になってからも、すでに一人の先生がフニャ高を去っていかれました。 9月にフニャ高へ来たばかりだった人。 仮の名を「O先生」としておきましょうか。
基本的に 先生が学年途中で辞めるのは異例のことなので、辞める事情はともあれ ちょっと遠くへ行くことになったので物理的にフニャ高に通うのは無理だから…ということが多い気がします。 辞めていくまでの期間が かなり急な場合もあるけれど、今までのケースではそれでも少なくとも『2週間後の金曜日まで』とか、そんな感じで、その先生が辞めるって事が 前もって周知のことになっていたわけ。
でも、O先生の場合は、いつの間にか居なくなっていた(・o・;;)…としか言いようがない。
冬休みが明けてからはもう O先生の代わりの先生が来ているので、今はモチロンO先生が辞めたことは周知の事実になっているけれど、O先生がいつ辞めたのかは、たぶん誰も知らないの(^^ゞ 冬休み前にはもう居なくなっていたけれど、いつから居なかったのかよく分からない。 ひょっとすると11月後半頃からすでに姿を見かけなくなっていたのかも???
O先生の席はワタシの席の右側 二人置いて三人目だったので、席は比較的 近かった。 でも、ワタシと違ってハンガリー語が不自由なわけでもないのに、O先生が誰かと雑談しているようなところを見た覚えがないのね~。 もちろん誰とも口をきかなかったわけはないだろうけど、O先生の向かい側の席の先生が「あの人、全然しゃべらないし…(-_-)」って言っていたのを聞いたので、ほとんど職場での会話がなかったんじゃないでしょうか?
そんな感じだったので、ハンガリー語力が不自由なワタシがO先生との会話がそれほどなかったのは当然といえば当然。 それでも、何回かは話したことがあって。
ある時、O先生に
「どうしてハンガリーに来たの?」
って聞かれたので、
「う~ん、特別に『来なくちゃならないような理由』があったわけじゃなくって~。 初めてフニャ高へ来たときは、その前にハンガリーに来たこともなかったし~。 家族や友達がいたわけでもなくって、知ってる人も居なかった。 しかもハンガリー語も全然知らなかったんだよね(^^ゞ」
…と事実をありのままに答えたらば、O先生はものすご~くビックリして、まるで化け物を見るような目でワタシを見ていたのが忘れられない。(ワタシのこの身の上話は、なぜかたいていの人に驚かれるんだが、O先生のは『人間じゃないモノ』を見ているかのような驚き方だった。)
誰も事情を知らないみたいなので想像するしかありませんが、O先生の場合は 半ば通勤拒否状態になって そのまま辞めることになったのかな…と思う。
今になって思えば、あの人、フニャ高に全然馴染んでいなかったよなぁ~。 イメージとしては、「怯えているネズミ」のような感じだったな。 怯える子ネズミちゃんには…フニャ高で先生するのは ただ辛くキツイだけの苦行だったでしょうね(^^ゞ 合わない場所に来てしまって気の毒だった。
O先生、今はフニャ高から解放されて元気にしているかな?
長くなりましたので、
今回は記事タイトルの「去る者」の部分だけ。

次回、「来る者」の話題へ進む予定です。
んでは、また明日~(^_^)/~