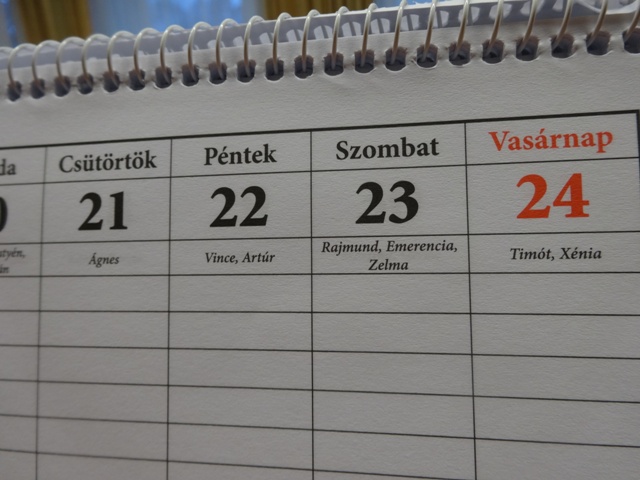この写真の家(↑)、右側の壁面のところで まるで切り落としたみたいに見えるんです。 たとえば、まるでロールケーキのように包丁でザックリ切り落としたかのように…???
だって家の屋根の形が なんだか不自然な台形じゃないですか?(^^ゞ
それに、手前側や向こう側には屋根のひさしがあるようなのに、右側だけは垂直にそそりたつ壁のみって、変じゃない?
家の形って左右対称とは限らないけれど、対称形じゃない場合でも 全体としてのバランスがとれて見えるモノじゃない? でもこの写真の家の場合は対称じゃないにも程がアル…というくらいに全体としてのバランスが奇妙。
でも、こういう「ぶった切ったような家」って、ハンガリーでは時々見かけます。
このような「ぶった切りの家」、ワタシは本当にぶった切ったんじゃないかと疑っている。(-“-) つまり昔は右側のほうにもつながって もっと大きい家だったのを、何らかの理由で 不要になった部分だけ取り壊し、必要な部分だけを残したんじゃないか…???…と。
ハンガリーの住宅の作り方などを観察していると、外壁はレンガみたいなものをガッチリ積み上げて建てているみたいなのね。(←イメージとしては「三匹のコブタ」の末っ子豚が建てたレンガのお家。) だから建てるのに日本とは比較にならないくらい時間をかけている。
以前、ウチの近所に 屋根がなくって壁だけが残っている「廃墟」がありました。
ある時、その「廃墟」に工事がはいり、
「邪魔っけな壁を取り壊して更地にするのかな?」…と思ったら、その逆。
ワタシには「廃墟」に見えた壁を修繕して、お家を建て直し、今では立派にな民家にリフォームされ、ちゃんと人が住んでます。v(@▽@)v
日本では まだまだ丈夫に建っている家でも取り壊して更地にしてから、新築するのをよく見るから、けっこう驚いたんでした。
だから、きっとバランスのおかしい「ぶった切りの家」も、不要部分をぶっ壊して 残りはそのまま活かしているんだと思うんだ。たぶん。(^^ゞ
ブダペストの街中だと大きい建物が
壁をピッタリ隣接して建てられています。

そういう大きい建物が建替えで取り壊されると、隣の建物はただの壁面。
表通りに面した側はデコラティヴだったりするのにね。