以前から ちょっと気になっていた食べ物。 それは『テーリ ファジ(Téli fagyi)』(^_^)
『テーリ(téli)』とは『冬の』という意味で、『ファジ(fagyi)』は『ファジラルト(fagylalt)』の略で 意味は『アイスクリーム』のこと。 『テーリ ファジ(Téli fagyi)』とは、すなわち『冬アイス』なり。 (以降『冬アイス』と書きます。)
この『冬アイス』、見た目は このようなアイスクリームのコーンみたいな感じ(↓)

売っている場所は冷蔵庫でも冷凍庫でもない。常温の場所です。 だから、「アイス」って言ってても本当にアイスクリームではなくて、見た目がアイスクリームっぽくなっているだけらしい。
日本にもアイスクリームコーン型の『グリコのカプリコ』(だったよね?)があるから、あれと似たような感じかな~?…と思っていて、実際に食べてみたことはありませんでした。 でも、ちょっと気になったので、やっぱり食べてみました(#^.^#)
かじってみた(↓)

意外にも中味は、常温でOKなクリーム。(カプリコと同じで、チョコレートか何かだと思っていた(^^ゞ) ちょっとバタークリームっぽくて、ソフト。 冷たくはないけれど、それなりにアイスクリームっぽいと言えないこともないかも。
カプリコとは全然違った。 カプリコのほうが美味しいと思うけど。(←あくまでもワタシ個人の評価)
ハンガリーの人は甘いものが好きなので ハンガリーにもお菓子はあるけれど、子どもが喜ぶ駄菓子っぽいものがあまりないな~…と思っていたんですが、『テーリ ファジ(Téli fagyi)』は かなり駄菓子っぽいお菓子です~♪
日本には「子ども菓子」とでもいうのか
パッケージなどからして いかにも子ども向けな感じのお菓子がありますが、
ハンガリーでは、あまりそういうのは見かけません。
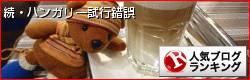
ハンガリー人は『甘いもの好き』なので
オトナもコドモも関係なくお菓子を食べるからかもしれませんが?
















